| ライオンのたてがみ 4 | ライオンのたてがみ 5 |
一週間が過ぎた。検死裁判は事件に全く光を当てることができず、新しい証拠が見つかるまで中断されていた。スタックファーストはマードックの調査をし、彼の部屋をざっと調べたが、何も出てこなかった。個人的に、私は全ての場所をもう一度歩き、考え直してもみた。しかし新しい発見は全くなかった。私の事件記録の中で、ここまで完全に能力の限界まで追い詰められた事件を読者は見い出せないだろう。どのようにしてこの謎を解決できるか、想像さえできないほどだった。そこに犬の事件が起きた。
最初にそれを耳にしたのは我が家の年老いた家政婦だった。彼女のような人物は、奇妙な電波で、田舎の出来事を収集できるのだ。
「悲しい話ですね、マクファーソンの犬のことですよ」彼女がある夜言った。
私はこういう会話に興味があるほうではないが、この話は注意を引いた。
「マクファーソンの犬がどうしたんだ?」
「死んだんですよ。主人を嘆き悲しんで死んだんです」
「誰から聞いたんだ?」
「まあ、ホームズさん、みんなこの話をしていますよ。ひどく嘆き悲しんで、一週間も何も食べていなかったんです。それで今日、ザ・ゲイブルズから来た二人の青年が、浜辺に倒れて死んでいるのを見つけたんですよ。主人が死んだまさにその場所で」
「まさにその場所で」その言葉が鮮明に記憶に残った。そしてこれは重大だというぼんやりとした感じが心に沸き起こった。犬には素晴らしい忠誠心という本能があるので、主人の後を追うことは不思議ではない。しかし、「まさにその場所で!」なぜあのわびしい浜辺が犬の死に場所でなければならないのだ?そんな事がありうるだろうか、犬もまた何か執念深い確執の犠牲になったというようなことが?そんなことがありえるのか・・・?そう、この思いつきは非常にあいまいなものだったが、既に何かが私の心に沸き起こっていた。数分後、私はザ・ゲイブルズに向かっていた。そこで私はスタックハーストを彼の書斎で見つけた。私の求めで、彼はサドベリーとブラントを呼びにやった。二人は犬を見つけた生徒だった。
「ええ、あの潮溜まりのちょうどその端に倒れていました」一人が言った。「死んだ主人の臭いを追っていったに違いありません」
私はホールのマットに置かれていた忠実な犬を調べた。エアデールテリアだった。体は堅くこわばり、目は飛び出し、足は捻じ曲がっていた。体全体に苦痛の跡が残っていた。
ザ・ゲイブルズから私は潮溜まりまで歩いて行った。太陽は既に沈んでいて、大きな崖の影が水の上に黒く落ち、鉛の板のように鈍く輝いていた。その場所はひっそりとして、二羽の海鳥が頭の上で輪を描いて鳴いている以外に生き物の痕跡はなかった。暗くなっていく光の中で、私は主人のタオルが置かれていた岩の周りの砂地に、ぼんやりと小さな犬の足跡を見分ける事が出来た。長い間、私は深く考え込んで立っていた。その間私の周りの影は濃さを増していった。私の心は駆け巡る考えでいっぱいだった。読者にはこれがどのようなものかお馴染みだろう。悪夢の中で、何か非常に重要な事があることを感じている。それを探していて、どこにあるかも分かっている。しかしそれがいつでも手の届かないところにある・・・。その夜、死体があった場所に一人で立っている時私が感じたのはそういう思いだった。その後、遂に私は振り返ってゆっくりと家に向かって歩き出した。
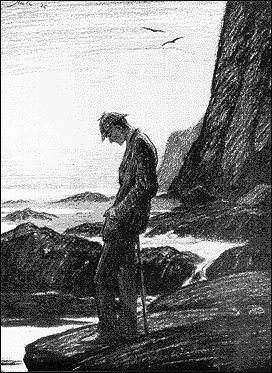
ちょうど道の頂上まで来たとき、閃光のようにそれがひらめいた。私はこれほどまでに熱心に求めていて、つかみそこなっていたことを思い出したのだ。ワトソンが書いていたので、読者はご存知だと思うが、私は変わった知識を多量に保有していた。科学的に体系付けはしていないが、それでも私にとって仕事上の要求を満たすには非常に有用だった。私の頭はあらゆる種類の包みが収められている、屋根裏部屋みたいなものだ。非常に沢山入っているが、何がそこにあったのかという事はおぼろげにしか分からない。私はこの事件にかかわりがありそうな何かが、そこにあったことに気づいていた。それはまだぼんやりとしていた。しかし少なくとも私はどのようにしてそれをはっきりさせる事ができるか知っていた。それは奇怪で、信じ難かったが、可能性は間違いなくあった。私はこれを最後の最後まで確かめるつもりだった。
私の小さな家には本がぎっしり詰まった大きな屋根裏部屋があった。私はそこに飛び込んで一時間探し回った。その後、私は小さな茶色と銀の本を手に出てきた。私ははやる心でうっすらと記憶があったその本の見出しをめくった。そうだ。これは実に信じがたくありそうもない考えだった。それでも私は実際にそうかをはっきりさせるまでは眠る事ができなかった。私が寝室に行ったのは遅くなってからだった。次の日の調査が待ちきれない気持ちだった。
| ライオンのたてがみ 4 | ライオンのたてがみ 5 |